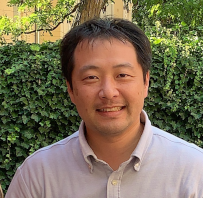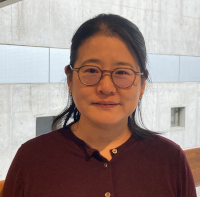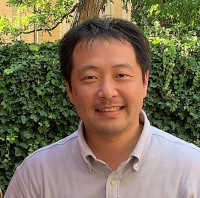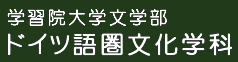田中 雅敏(たなか まさとし) 教授
専門分野
ドイツ語学、理論言語学、歴史言語学
現在取り組んでいる研究テーマ
- ドイツ語の名詞複数形の歴史的分析
- 不規則動詞の母音交代の類型
- 文法化
主要著書・論文
- 「現代ドイツ語のいわゆる不在構文について」『東洋法学』68巻1号, 2024年, 175-183.
- 「古ゲルマン語の語アクセント固定化と複数形語尾について」『東洋法学』64巻2号, 2021年, 67-86.
- 『学際的科学としての言語学研究』ひつじ書房、2020年、共編
- 「古ゲルマン語における名詞の分類と現代ドイツ語の複数形について」『東洋法学』63巻1号, 2019年, 151-170.
- 「現代ドイツ語のシグナル語尾について」『東洋法学』62巻3号, 2019年, 407-426.
- 「ドイツ語の定動詞第二位関係文について」『東洋法学』60巻2号, 2016年, 13-26.
- 「ドイツ手話における意味役割の階層性について」『東洋法学』58巻1号, 2014年, 53-64.
- 『講座ドイツ言語学 第1巻 ドイツ語の文法論』ひつじ書房、2013年、共著(第2章担当)
- 「manabaによるドイツ語eラーニング環境の構築」『ドイツ語情報処理研究』22号, 2012年, 21-37.
- 「定動詞後置を伴わないドイツ語の副文にみる定動詞位置の動機づけ」『DER KEIM』35号, 2012年, 13-30.
- 「Moodleによる独検対策eラーニング環境の構築とその運用」『東洋法学』54巻1号, 2010年, 303-322.
- Zur Anhebugsmotivation des finiten Verbs: Syntaktische Markierung von Satzmodi. In: TOYOHOGAKU 53/2, 2009, 342-356.
- 「Moodleによる初修言語CALLについて(3)」『言語文化研究』28号, 2009年, 21-44.
- 「ゲルマン諸語における定動詞移動の歴史的変遷と定動詞位置の最適性理論分析」『広島ドイツ文学』22号, 2008年, 11-28.
- Interaktion von Topikalisierung und Verbzweitstellung: Optimalitätstheoretische Analyse In: Studies in European and American Culture 14, 2007, 49-69.
- Syntaktische und semantische Analyse zur Topikalisierung im Deutschen. Unpublished dissertation (Hiroshima University) , 2007.
- 「定動詞第二位構文の出力最適性を決定する制約について」『欧米文化研究』13号, 2006年, 39-58.
- 「ドイツ語の名詞の性割り当て規則:ドイツ語に取り入れられた日本語由来の名詞の性をみる」『欧米文化研究』12号, 2005年, 133-150.
- 「ドイツ語圏の外国人社会融合プログラム―2つの社会とアイデンティティ」『広島ドイツ文学』18号, 2004年, 65-80.
- 「Terraを使ったオンラインドイツ語学習プログラムの構築」『ドイツ語情報処理研究』15号, 2004年, 21-34.(吉田光演と共著)
- Thema-drop und pro-Form im Japanischen. In: Neue Beiträge zur Germanistik 32, 2004, 95-107.
- 「ドイツ語の非連続構文の部分的削除アプローチ」『広島ドイツ文学』17号, 2003年, 83-100.
- 「機能的主要部制約の類型論」『欧米文化研究』10号, 2003年, 1-17.
- Anti-Bewegungsanalyse der Nominalphrasen in der A’-Position des Japanischen. In: Die deutsche Literatur (Doitsu Bungaku Ronshu) 35, 2002, 102-110.
- Zur Deklination innerhalb der deutschen nP, In: Hiroshima Doitsu Bungaku 14, 2000, 93-108.
- 「現代ドイツ語における分離話題化構文に関する一考察」『広島ドイツ文学』13号, 1999年, 45-62.
参考書・教科書・翻訳など
- 『ドイツ語文法大全』語研、2024年、共編著
- 『1ヶ月で復習するドイツ語基本の文法』語研、2022年
- 『基礎語彙に乗せるドイツ語積み増し360語』語研、2021年
- 『ゼロからスタートドイツ語(文法編)』Jリサーチ出版、2021年
- 『中級学習者のためのドイツ語質問箱 100の疑問』白水社、2019年
- 『わたしのドイツ語』白水社、2012年
所属学会
日本独文学会、日本独文学会教育部会、ドイツ語情報処理学会、日本独文学会関東支部、ドイツ文法理論研究会、広島独文学会 など
近年の主要講義・演習
- 「言語・情報コースゼミナール」— 社会言語学入門:ドイツ語の多様性
- 「言語・情報講義」— 論理学入門
- 「言語・情報講義」— 文法理論入門
- 「言語・情報入門ゼミナール」— ドイツ語学入門
- 「ドイツ語学演習」(大学院)— 統語論と意味論のインターフェイス
文学部で/私のゼミで学ぶ人たちへ
子どもの頃からことばに興味があり、日本語が「WHOは24日、世界的パンデミックが終息の方向にあることを発表した」という文のように、ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベットを混在して使っているのに対し、英語の文が26個のアルファベットの組み合わせだけで作られていることが新鮮でした。使われる文字や文法(語順)は違いますが、人間は、生まれながらに持っている言語能力としては共通の(普遍的な)ものを持っており、それを特定の言語体系に合わせていくうちに、その言語の文法を習得していきます。私が担当するゼミでは、人間がことばをどのように獲得しているのか、またことばはどのようにコミュケーション手段として機能しうるのか、などについて、ことばを学問として取り上げます。
また、2019年度から、オーストリアに姉妹都市を持つ香川県さぬき市の姉妹都市交流のお手伝いをしています。さぬき市の子供たちがオーストリアの子どもたちに書いた手紙を翻訳してオーストリアに届ける活動をしています。一緒にこの活動をしてくださる学生がいれば、大歓迎です。「現代地域事情ゼミナール」を担当するときにはこの活動をテーマにします。
ドイツ留学の相談や国際交流・異文化理解の話など、みなさんといろいろ意見交換・情報交換ができれば嬉しく思います。みなさんの4年間が有意義なものとなるよう、教員は必要なだけ利用してください。